音楽が英語をひらく鍵になる
教科書だけでは伝えきれない英語の魅力を、一曲の洋楽が一気に引き出してくれることがあります。
narynglishでは、Rachel Plattenの “Fight Song” を使って、小学生から大人まで、幅広い学習者と英語の楽しさ・深さを共有してきました。
この活動は、学校現場での授業づくりや評価にも応用可能な実践例としても注目しています。たとえば:
-
サビ部分の語順を並べ替える問題を定期考査の一部に出題
-
「この曲が好きか?その理由を英語で書く」ライティング課題にする
-
歌詞を元に自己表現・スピーチの導入活動にする
音楽を入り口にすれば、文法・語彙・構文・感情表現まで、多角的な英語学習が自然に広がっていきます。
洋楽を取り入れる4つの利点
感情が動く=記憶に残る
楽曲のメッセージに共感することで、英語が「ただの言葉」ではなく「伝えたい思い」になる瞬間が生まれます。
文法・語順への自然な意識
「意味が伝わる並びはどれ?」という視点で取り組むことで、語順への感覚や構文理解が育ちます。
リズム・イントネーションの習得
歌は発音の型やリズム感を身につける絶好の教材。話す前に「歌ってみる」ことで、無理なく音声化のステップに進むことができます。
音声変化に気づく耳を育てる
歌うことで、自然と**英語らしい音のリズムや省略(音声変化)**に意識が向くのも、洋楽を使う大きな利点です。たとえば “starting right now” の箇所では、-ing と right がつながり、とても短く発音されます。初めは「ん?なんて言ってるの?」となる部分も、何度か歌うことで耳と口が慣れ、リスニング力の向上にも直結します。
理論的背景:InputからOutputへの架け橋
英語学習において、「聞いて終わり」「読んで終わり」になりがちな活動を、学びの循環(input → intake → output)として機能させることが、効果的な習得の鍵になります。
この観点で、“Fight Song”などを使ったアクティビティは、非常に優れた教材です。ここでは、Rod Ellis(2003)やSwain(1995)の研究を参考に、その理論的背景を説明します。
意味のあるInputがあってこそ、Outputが生まれる
Ellis(2003)は、学習者が新しい表現や語彙を自分の中に取り込むには、「意味に基づいたインプット」が必要だと述べています。歌詞というのは、単なる例文ではなく、感情やストーリーが込められた「意味のある言語インプット」です。
Outputが深い理解と習得を促す
Swain(1995)の「出力仮説(Output Hypothesis)」では、アウトプット(話す・書く)をすることで初めて、自分の言語知識の「穴」に気づくとされています。並べ替えやライティング、歌詞への反応を書く活動が、まさにその機会になります。
反復が「定着」と「応用力」へつながる
歌の繰り返しによって、語順や表現が自然に体に染み込み、他の表現にも応用しやすくなります。”This is my fight song” → “This is my story” など、構文の転用も期待できます。
学習者のエージェンシー(主体性)を育てる
さらに、最近の教育理論では、学習者が「何を、どう表現するか」を自ら選ぶ力=エージェンシー(agency)が、深い学びに不可欠だとされています(Mercer, 2019)。
自分でお気に入りのフレーズを選ぶ、自分の気持ちに合う言葉に言い換えるといった活動は、学習者が受け身ではなく自らの言葉として英語を選び取り、使おうとする瞬間を生み出します。これは、言語習得の質を大きく高める要素であり、Output Hypothesisと共に、現代の英語教育を支える大切な視点です。
レッスンの流れ(narynglish実践例)
モアナの映像付き “Fight Song” を視聴
視聴前にMoanaという映画について知っているか、などのやりとりをしておくと、興味関心がグッと高まります。また、歌だけではなかなか集中して聴くことができなくても、映像があることで物語と曲がリンクし、自然と引き込まれます。
私が使用したMoana版「Fight Song」の動画はこちら:[YouTubeリンク]
Wordwallでサビの歌詞を並べ替え
This is -.から始まるのでこれまでに見聞きしたことのある表現なので、音と文字を繋げる活動に最適。また、Wordwallのアプリを使うと簡単に並べ替える語順・構文の意識づけになります。実際に並べ替えをやってみたい人は、名前(nickname可)を入力し、下のサイトをお試しください♫
Wordwallの並べ替えクイズはこちらから体験できます↓
並べ替えた歌詞の意味を確認
並べ替えが終わったら、各文の意味を確認することで、単語レベルから文全体の構造への意識を高めます。この段階では、表現の背景や感情も一緒に掘り下げていくと、より記憶に残りやすくなります。
字幕付き(英語+日本語)でもう一度視聴
次に、英語字幕+日本語訳つきの動画を使って再視聴します。音・意味・文字が三位一体で結びつくことで、聞き取りやすさが飛躍的に上がるフェーズです。
視覚と聴覚の連動を意識することが、インプット定着の決め手になります。私が使用した日英対訳が確認できる「Fight Song」の動画はこちら→:[YouTubeリンク]
自分の言葉に言い換えてみる/好きなフレーズを共有する
このフェーズでは、インプットした歌詞をもとに、学習者が自分の言葉で表現し直す活動へと発展させます。
たとえば、“This is my fight song” を、“This is my dream plan” や “This is my art piece” のように自分自身の文脈に合わせて言い換えることで、構文の応用力が養われ、自然な形で自己表現へとつながります。
また、“Starting right now, I’ll be strong” の構造を応用し、“Starting this week, I’ll try ___” のように短期的な目標を英語で立てる活動へとつなげることもできます(例: “I’ll try to wake up early.” “I’ll try to talk to my friend in English.” など)。
こうした言い換えや選択の活動を通して、学習者は**「どの表現を使うか」「どう伝えるか」を自ら判断し、英語に自分自身の意味を与えることになります。これは、SwainのOutput Hypothesis(1995)が示すアウトプットの重要性**に加えて、近年注目されるエージェンシー(agency)――学習者の主体性と選択の力を育む上でも、非常に価値のある取り組みです。
単に与えられた語彙や構文を練習するのではなく、自分の声・考え・感情を乗せて表現する体験こそが、言語学習を深く、意味あるものにしていきます。
小学生向けの工夫:言い換えが難しい場合は?
小学生など、まだ自由な英作文が難しい学習者に対しては、「お気に入りのフレーズを選び、その理由を話す」といった活動にシフトすると、心理的負担が軽減され、表現に対する親しみが育ちます。
-
たとえば、並べ替えで出てきた “I still believe.” や “I’m alright.” を取り上げて、
「どのフレーズが好き?」「なんで?」という形で短いやりとりを行います。
→ 小学生の回答例:「“I still believe” が好き。あきらめない感じがするから!」
→ 「“I’m alright” が好き。今の自分にも言いたいから!」
こうした共有の場を通して、「使ってみたい英語」が生まれやすくなり、表現が子どもたちの中で“育っていく”感覚が生まれます
まとめ:教育現場でもっと音楽を
“Fight Song” のような洋楽は、ただの娯楽ではありません。
そこには、文法・語彙・構文・リスニング・発音・感情表現――英語学習に必要なすべてが詰まっています。
並べ替え問題やライティング課題として扱えば、評価に直結する教材としても活用可能ですし、何より、「英語って楽しい」「使ってみたい」という前向きな気持ちを育てる力があります。
たった一曲が、英語を“生きたことば”として動かすきっかけになるかもしれません。
そして、その小さな変化を見つめ、言葉を育てる伴走者としてそばにいるのは、教室にいる私たち一人ひとりです。
投稿者プロフィール
-
英語指導歴20年以上/英検1級/元高校英語教員
長崎県諫早市の英語教室「narynglish」主宰 吉田恵子(Nary/ナリ)
【学歴・職歴】
• 大学在学中 カリフォルニア州立大学フレズノ校へ1年間交換留学
• 2000年 長崎県公立高校教諭として採用
• 2008年 早稲田大学大学院教育学研究科 修士課程修了
• 2023年 公立高校教諭を退職後、narynglishを起業
一人ひとりの「わからない」を大切に、「つまづき」を飛躍のチャンスに変える英語レッスン。
実践的な英語力に加え、自分で考える力・継続力・非認知能力を英語を通して育みます。
中学生、高校生が将来にわたって英語を使いこなせるよう、英検対策・定期テスト・留学準備を土台から支援。
「安心して取り組める」「前向きになれる」と評判で、naryとまた学びたい!と言ってもらえる英語教室です。レッスン方法は、対面・オンライン・ハイブリッドの形式から選べます。
最新の投稿
 英語教室ナリィングリッシュ紹介2026年1月9日時間軸に捉われない | 年末年始のレッスン生たち
英語教室ナリィングリッシュ紹介2026年1月9日時間軸に捉われない | 年末年始のレッスン生たち 英語教室ナリィングリッシュ紹介2026年1月2日2026年のテーマ「地」:根を育てる
英語教室ナリィングリッシュ紹介2026年1月2日2026年のテーマ「地」:根を育てる 英語教室ナリィングリッシュ紹介2025年12月29日2025年のテーマ「脱」から振り返る教室の1年
英語教室ナリィングリッシュ紹介2025年12月29日2025年のテーマ「脱」から振り返る教室の1年 英語おすすめ本2025年12月26日子どもの学びを見る、新たな視点を与えてくれた一冊
英語おすすめ本2025年12月26日子どもの学びを見る、新たな視点を与えてくれた一冊

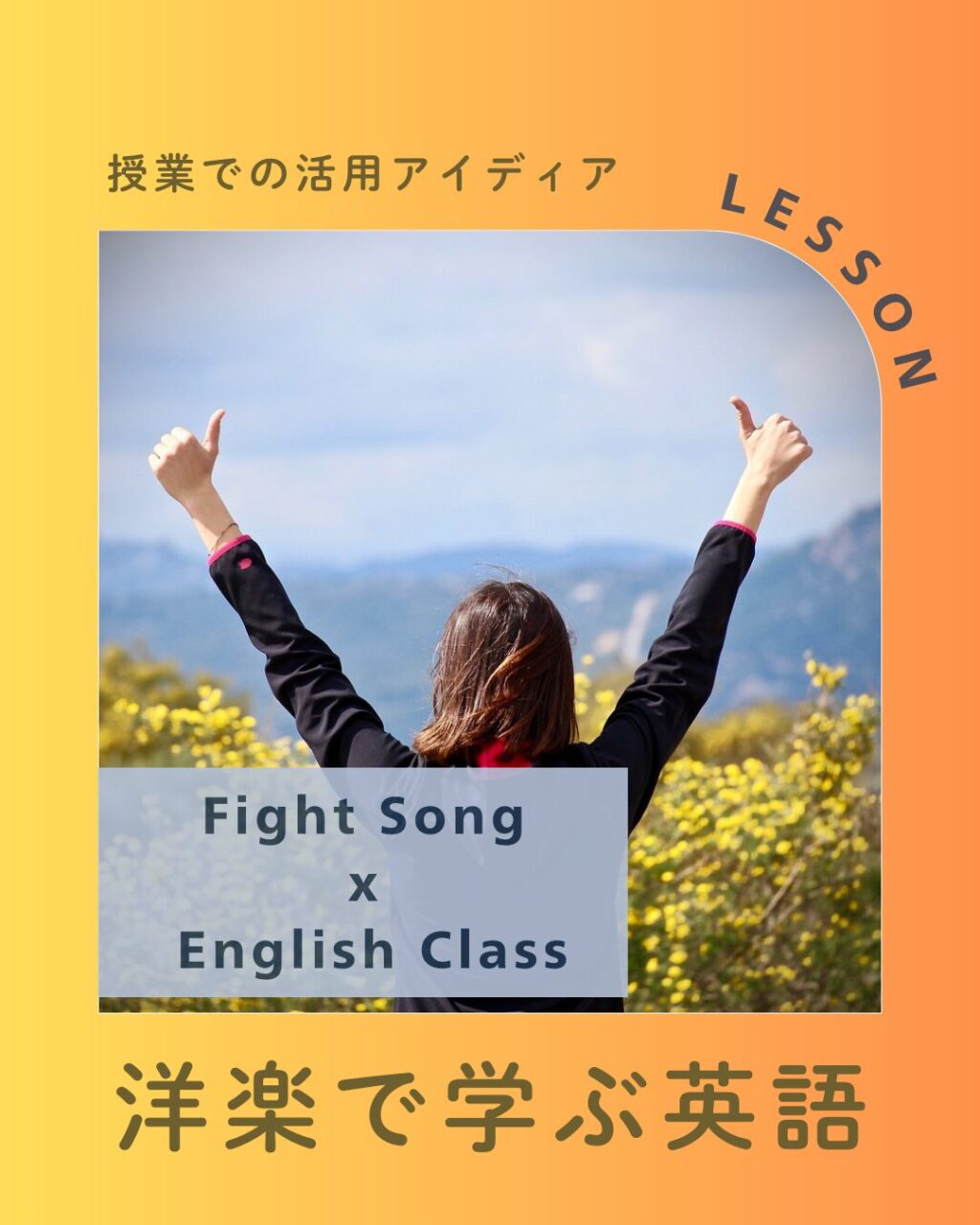


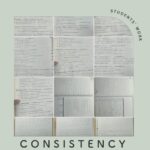
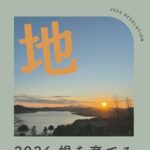
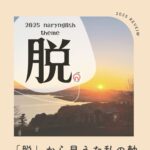
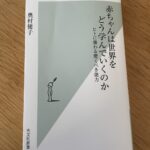
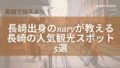

コメント